最新記事 by さるぽて (全て見る)
- 理系院卒が事務系職に就職/転職するのはもったいないのか…?〜後悔しないために必要な考え方 - 2019年9月27日
- 単結晶作りのコツ〜万策尽きてお祈りするしかない貴方へ〜 - 2019年6月12日
- 研究室の外国人研究員と仲良くなれ - 2018年9月27日
- バーコードは絶滅する?超効率的な製品管理を可能とするRFIDの種類と原理 - 2018年9月9日
- 危険物取扱者試験甲種とは。学生時代の着手で将来の自分に貢献しとく? - 2018年8月5日
こんにちは、最近様々な技術を調べては新規事業を考えているさるぽてです。
唐突ですが・・・
おそらくほとんどの方は回転寿司屋さんで、食べ終わったお皿をベルトコンベアーの下に流すとなぜか枚数がカウントされて、5枚ごとに謎のガチャガチャを引かされた経験ありますよね。
一見ただのプラスチックでできたお皿がゲートをくぐっただけなのになんででしょう。バーコードみたいなものも描いてないし、まさか1卓ごとカメラで画像認識できる装置がついているはずもありません。
その答えは今回のお題、”RFID”という通信技術にあります。
今はまだまだ限定的な使われ方ですが、今後広く展開されると予想される代物です。
というわけで、今回の記事では主にRFIDの原理と現状について基本的な部分をまとめました。
ぜひ未来のRFIDの進化によって可能になる便利な社会を想像してみてください。
目次
(CMです)
理系とーくの公式LINEに登録すると…
無料イベント、理系バー、科学系オンラインコミュニティの情報に加えて、
LINE登録特典としてプレゼント(有機化学のスライド資料)もお受け取りが可能です!
↓
RFIDの基礎知識
早速ですが、RFIDそのものの説明をしていきます。
そもそも「RFID」という名前の意味ですが、これは単語の頭文字を繋げた略語です。
Radio
Frequency
IDentifier
ラジオ波を使ったIDってことですね。
後述するように、色んな種類のRFIDがあるのですが、RFIDの持つ機能は”接触させずともICチップにある情報のやりとりができる機能”と言えると思います。

RFIDの原理
まずはそもそもどのようにして非接触でデータのやり取りをしているのでしょうか。
その答えは、電磁波に情報を載せているんですね。電磁波を飛ばせばデータのやり取りができるので、読み取り機(リーダー)とチップは繋がってる必要がないわけです。
ここで”波に情報を乗せる”というイメージが湧かない人もいると思いますが、非常に簡略化するとこのようなイメージです。

上記の様な電波で通信するとします。ここで、

この様に一部振幅を変えた波を送ります。
すると、読み取る側は「ん?この部分の波形が変わってるぞ」という変化を検知することになり、その部分が情報としての意義を持つというわけです。(シンプルに二進法の例を考えるなら、最初の波が0、大きいところが1、その次の波は0の情報を持つイメージです。)
アクティブタグかパッシブタグか
さて、ここからRFIDの中でも複数種類に分かれます。

まず大きく分かれるのが、パッシブタグかアクティブタグか、という分類です。(ちなみにタグというのはよくある普通のバーコード等と同じようなサイズ感のものと捉えてもらってよいですが、この場合ではICチップを内包した札やシールです。)
このパッシブタグかアクティブタグかの分類はとても簡単で、判定の基準はタグ一つ一つに「電源が有るか無いか」です。
パッシブタグ:電源無しのタグで、リーダーから電磁波を受けるとICチップの情報を飛ばす。
アクティブタグ:電源有りのタグで、タグ単体で自発的に情報を飛ばすことができる。
一瞬、アクティブタグの方が一人でも頑張れて便利そう、って思われるかもしれませんが、すごいのはパッシブタグですよね。
「電源無しでどうやってICチップ動かすんだよ・・・!」って思いません?
しかも、タグそのものに電池がいらないので、
・一枚あたり低コスト→原価が安いものに使っても利益を圧迫しにくい
・電池の寿命の心配無し→メンテナンス不要、貼り替えの頻度低下
・小型化しやすい→小さい箇所にも貼れる
といった長所があり、現在注目を集めているのは断然パッシブタグです。今回もそちらの話に絞って説明させていただきます。
周波数による分類
パッシブタグの中でもさらに用いる電磁波の周波数(Hz、1秒間に何度振動するか)により分類は分かれます。

おおよその分類ですが、RFIDに関してはこの様に呼び分けることが多いです。
LF (Low Frequency): 数kHz〜百kHz程度
HF (High Frequency): 数MHz〜数十MHz
UHF (Ultra High Frequency): 数百MHz〜数GHz
マイクロ波: 数GHz〜数十GHz
タグ側と読み取り側と、使える周波数を合わせないといけないのである程度よく使われる規格ができますね。
さて、実は周波数が異なると、ICチップに電力を供給する技術が変わってきます。
低周波(長波長)のものは電磁誘導方式
LF (Low Frequency): 数kHz〜百kHz程度
HF (High Frequency): 数MHz〜数十MHz
実は冒頭の回転寿司のお皿の件はこのLF帯のRFIDを使っています。
もうお判りかもしれませんが、どうしてしっかり枚数をカウントできるかというと、流しで電波をキャッチしたお皿のRFIDタグが応答しているわけです。
さて、これら低周波数のものは電磁誘導方式で電力を得ています。
非常〜〜にざっくりした絵ですが・・・。

(1):交流流す
(2):電磁波が発生し、タグ側のアンテナを通過
(3):交流が流れてタグ起動
高校物理を取っていた方だったら電磁誘導という単語だけでピンときているかもしれませんが、磁場の変化があると打ち消すように電流が流れるんでしたね。
これらの周波数帯の強みは、比較的水に吸収されにくいことです。
逆にこれらの周波数帯の弱みとしては、電磁波は長距離まで十分な量が届かず、通信距離はせいぜい数十cmです。そのくらいの距離だとそれでも十分な場面ともう少し距離が欲しい場面とがありそうですよね。
高周波(短波長)のものは電波方式
続いて、
UHF (Ultra High Frequency): 数百MHz〜数GHz
マイクロ波: 数GHz〜数十GHz
上記の比較的高周波なものは電波方式と呼ばれており、電波をそのまま整流器で電流として取り出しているようです。(この辺学術的詳細不明なので詳しい人教えてください。)
これらのメリットは、まずは先述のLF、HFと比較すると通信距離が長いことです。およそ数m届きます。
もはやLFなどもこの方式にすれば良いのではと思うかもしれませんが、
UHF等は高周波、つまり短波長である点、
これらの電波の方が直進性が高い点、
で、エネルギー的に可能なのがこれら高周波帯になるのではと考えています。こちらももし専門の方がいらっしゃったら是非コメントをください。
また、高周波ということは、単位時間の波数が多いということで、情報通信量も多いです。(データのやり取りで説明した通り、一つ一つの波の振幅やら位相を変えてデータを送るので、1秒あたりに出る波が多いということは1秒あたりに送信できるデータも増えます。)
一方、LF、HFのメリットと逆に、水には弱いです。
また、物理的な回折の観点で、マイクロ波に関しては波長がかなり短く、障害物の裏まで回り込みにくいという欠点もあります。
RFIDの現状のメリットとデメリット
他に非接触で情報通信ができるタグといえば、例えばバーコードがありますよね。
それと比べてRFIDにはどの様な長所短所があるでしょう。
RFIDのメリット
はじめにメリットです。たくさんあります。
電磁波さえ通れば障害物があっても読み取れる
箱の中の商品のバーコードを読み取るのって無理ですよね?赤外線を通すのならできるでしょうが、比較的可視光域に近いですし、多くの入れ物は吸ってしまうのと、そもそも狙いを定めることができません。
ところが条件付きでRFIDならできちゃいます。
ダンボールや袋は電磁波をほとんど吸収しません。また、
・リーダーから電磁波当てる
・タグから跳ね返ってくるのをキャッチする
これさえできれば情報通信可能なので、狙った場所に正面からしっかり当てる必要がありません。
複数同時に処理可能
これも大きな強みで、タグが10個あるとします。
これに電磁波を当てると、それら10個を一気に読み取ることができます。
バーコードだと一個一個にしっかり狙いを定めて当てないといけませんよね。
(物によって)書き込みが可能
後から書き込みが可能なものもあります。
それはICチップを使っているからで、データの中身を書き換えるという他の電子機器では今や当然の機能をRFIDタグにも持たせた、とも言えます。
バーコードだったらあの黒い線を書き換えないとできませんね。
(物によって)様々なセンサーにもなり得る
これ、面白いと思うんですが、例えば温度や圧力等を読み取れるRFIDタグなども存在します。
RFIDのデメリット
続いてデメリットです。
コストが高い
現状一番のデメリットでしょうね。
大量生産で低機能なタグを用いても一枚数円はかかりますし、一般的にはまだまだ10円程度と考えて良いと思います。一枚一円未満で作れるバーコードと比べると高いですね。
家具程度の大きさになれば許容範囲かもしれませんけど、うまい棒とかだったら値段が50%増しになっちゃいます。
一回貼って何度も何度も使うならいいですが、商品のバーコードのように使う回数が限られているものの代替としてはかなり重たいコストになります。
金属や水があると機能しにくい
バーコードだって覆われていたら厳しいので、実質RFIDならではのデメリットではないかもしれませんが、
RFIDは電磁波が誘電体に吸収されてしまうので金属や水があると精度が大幅に低下します。
物理的に壊れやすい
むき出しになってはいないとはいえ、ICチップが心臓部なわけで、お世辞にも衝撃に強いとは言えません。
もちろん包装部分を強化すれば低減できますが、そうしたらコストが・・・。
これまでのRFID応用事例
タグとしての最も先駆的な例では、図書館への導入があります。2000年代前半のことです。
本に貼っておいて、棚卸し・貸出記録の簡易化や、貸出手続き前にゲートを通るとセンサーが鳴るセキュリティゲートなどに使われています。

(デメリットの項目で記載した一つ目と二つ目のデメリットを読み返してみればわかると思います。)
また、最近の有名なRFIDタグ適用例と言えば”ユニクロ”です。
例えば、あんな高いとこにあるジーパンの棚卸しとか大変ですよね。
一方RFIDタグだとどうでしょう?
UHFのように比較的長い距離通信可能なRFIDを使えば、離れた場所から複数同時に棚卸しできちゃいますよね。
(ユニクロの場合、製造から行うSPA企業であることでタグを有効活用できている背景があります)
この辺のビジネスに関してもう少し踏み込んだ記事は僕のサイトにありますので参考にどうぞ。
「RFIDタグの応用事例」
今後見込まれるRFIDの技術的進歩
これはもちろん誰にもわからないことですが、個人的には次の二つを思っています。
印刷によるコスト低下
もちろんRFIDが最優先で解決すべき問題はコストです。コスト低減は間違いなく取り組まれるでしょう。
そしてそれはやはりこれまでの歴史通り、大量印刷が一つの候補になるのではないかと思います。
最近は導電性インキの開発だとかも進んでいますし、タグ何万枚分が一辺に印刷されて、くり抜かれたりすればかなり安くなりそうですよね。
高周波数の利用
これまでの進化の延長線上ですね。やはり高周波のものは小さなアンテナで済むのでさらなる小型化も可能ですし、通信量も増やせます。
未来の携帯回線として5Gの開発も進められていますが、実用化に向けてはそれと同じような障壁を超えていくことになるんでしょうね。
(CMです)
本サイトを運営する理系とーくのLINEができました!
研究者・科学好きの方とつながれるイベントの情報等を配信します!
ぜひ友だちになってやってください。
↓

![]() ↑
↑
「理系とーくLINE」の友だち追加はこちら
近い将来、バーコードは絶滅してRFIDで管理する世界に
このようにまだまだ発展途上のRFIDですが、技術ベースでのポテンシャルの高さはお判りいただけたでしょうか。
実は経産省は既に将来コンビニのタグは全てRFIDにすると言っています。
そうすればコンビニのレジは無人で済むようになり、人々の利便性を損なうことなく(むしろ高めた上で)必要な労働力を減らせますよね。そういうのって現代ではAIの役割というイメージが強いですが、元来そうやって人間は技術に必要労働力を預けてきました。
もしRFIDが世の中にもっともっと浸透すれば今では思いつかないような用途にも発展すると思いますし、ますますRFIDの守備範囲は広がっていくでしょうね。







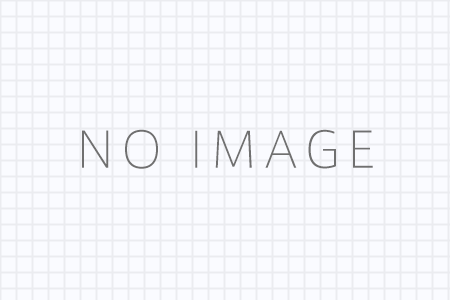










コメントを残す